10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第22話は、突然始めたプロモーター稼業について。まだ田舎の風情が残っていた岡山に大学生として舞い戻って悲しかったのは、好きなアーティストのライヴがないこと。それなら、自分で「やっちまえ」ってことになるのですな。
70年代半ばの岡山は、関西と広島の谷間で取り残された街のように見えていた。
そう映っていたのは、最も多感な高校時代を、当時は日本で二番目の大都市、大阪で過ごした反動だったんだろう。実際に住んでいたのはけっこう田舎の深南部、南河内郡(現在は堺市に編入)だったとはいっても、ちょいと電車に乗れば「なにか」が起きていた都会に出ることができる。それに比較すると、ずいぶん田舎に見えたのが大学で舞い戻ってきた岡山。ここに都市の喧噪なんぞ全く感じることはなかった。
あれから半世紀近くを過ぎた今、駅周辺はかなり都会に見える。こうなったのは瀬戸大橋ができたことで四国と本州をつなぐハブとして岡山が機能し始めたことに起因しているんだろう。新幹線の進化や高速道路網の拡張も、それに拍車をかけている。東京での40年ほどの生活に区切りをつけて、岡山に移住して半年と少し過ぎた昨秋、ここを初めて訪ねてきた友人に「けっこう、都会なんですね」なんて言われて、「まぁな」と応えていたように思う。ドンキもあれば、MUJIもユニクロもある... といっても、結局、どこの地方都市も画一的な顔を持つ無個性の「都市」になったに過ぎないと言った方がいいのかもしれない。
が、学生時代のここにはなにもなかった。広島のフォーク村が噂になり、大阪では関西フォーク・シーンが騒がれていた一方で、そういった動きはほとんどなかった。もちろん、なにかをやっていた人達はいたし、マイナーな動きは確かに存在した。が、それがメディアを通じて騒がれることもなければ、大きな影響力を持つことはなかった。
1970年に自主制作され、後にエレックから発売されることになったのが、広島フォーク村をドキュメントしたような伝説のアルバム『古い船を いま 動かせるのは 古い水夫じゃないだろう』(オリジナル:FSL-443-5027、エレック盤オリジナル:LP-1001)。ここに吉田拓郎の原点を見ることができる。
だからなのか、鬱積していたのがけっこうな欲求不満。大阪では毎週のようにフォークやロック系のライヴもあったし、いわゆる外タレの来日公演も珍しくはなかった。ところが、岡山には... 誰も来ない。とまで言ったら、語弊があるが、自分が好きだったり、気になっていたアーティストのライヴなんぞ皆無に近い状態だった。
それでも地元に呼び屋、プロモーターが生まれていた。今では中四国地方で最も大きな影響力を持つ会社のひとつ、夢番地がそれだ。この創始者の善木氏とは当時から面識があって、今も懇意にしていただいているんだが、当時、この会社が自分が好きなアーティストを岡山に呼ぶことは希だった。それをして「彼らはメジャーしかやらない」と決めつけたのは若気の至りなんだろう。それから40数年後に彼と飲みながら、「そんなことないよ」と否定されるんだが、あの頃の自分にはそう映っていた。記憶をたどれば、「彼らもやるじゃん」と思わせた最たるものが、トム・ウェイツの岡山市民会館でのライヴ。一度しか来日していない彼のライヴをこの岡山で実現させたのは驚異としか言いようがない。また、岡山理科大学の学園祭に上田正樹とサウス・トゥ・サウスを突っ込んだこと。といっても、遙か彼方の出来事。実際に、彼らの仕事なのか、あるいは、大学の学生がリクエストしてこうなったのか正確にはわからないし、当時の噂でそう聞いたに過ぎない。
大学祭や学園祭に関わる若者が独自にアプローチしたり、あるいは、プロモーターを通じて、ニューミュージックからフォークやロック系のアーティストが姿を見せるようになっていたのがこの時代。岡大でも神戸のバンド、アイドルワイルド・サウスを呼んだ仲間がいた。サザン・ロックが好きな人なら想像できるだろう。ザ・オールマン・ブラザーズ・バンドのセカンド・アルバムのタイトルをそのままバンド名にした彼らの音楽は、そんなアメリカ南部への憧れがそのまま形になっている。北陸のめんたんぴんや越中屋バンド(後のT-バード)あたりも同じような流れにいて、今でも、彼らのアルバムを聞くとやたら新鮮に響くのが面白い。
1976年に発表されたのが、オールマン・ブラザーズを感じさせる神戸のバンド、アイドルワイルド・サウスが残した唯一のアルバム『Keep On Truckin'』(FLD-10004)。このリンクは「Lynyrd Skynyrdの初来日時にオープニングアクトで演奏した時の音源」とある。
それはさておき、学生だってなんだって、バンドやアーティストを呼べるという、時代の空気もあったからだろう。
「だったら、自分でやればいいじゃないか」
と、そんな発想で、プロモーター稼業に手を出すことになるんだが、その伏線となったのは演劇部の部員として黒テントの情宣活動を手伝ったことだろう。やっていたのは単純なポスター貼りやチラシまきに、チケットの手売り... もちろん、ただ働きのボランティア。一般的に言えば、「なにが嬉しくて、そんなことしてんの?」と、疑問に思われるんだろうけど、大阪で春一番を手伝ったのと同じ感覚だった。単純に面白いものを見たい、知りたい、多くの人たちに知ってもらいたい。それだけのことだった。
自分は、おめでたいのか、お人好しなのか、ただのバカなのかもしれない。いつだっけか、早稲田小劇場から別れて演劇群「走狗」を始めたという方が、演劇部を訪ねてきて、「岡山で公演をしたいんですけど、情宣をお願いできませんか」と尋ねられたことがある。「いいよ」と、即答したら、けっこうぽかんとした顔をして「え、ホントにいいんですか?」と返ってきたものだ。「そんな人、ほとんどいませんから」ってことだったらしい。
なんで一銭にもならないことをやったのか? よくわからない。でも、楽しかった。それだけで充分。退屈きわまりない大学への反動もあったかもしれない。一応、ある程度授業には出て、興味のあったフランス語やドイツ語の勉強も真剣にやっていたと思う。専攻していた哲学科には気に入った教授がいて、彼の講義でジャン・ポール・サルトルの原書を読むのも面白かった。でも、適当に授業に出ていれば単位は取れる。哲学科なんぞ卒業してまともな職にはありつけないだろうと、教員免許をとるための講義も受けたみたり... でも、日本の大学なんて入ってみれば、簡単に卒業できる。2年目を終わった時点で卒業に必要な単位の90%は取得していたし、教育実習さえやれば教員免許も取れるぐらいにはなっていた。あとは週に一度講義を受けて卒論さえ書いたら卒業できる。大学の講義ってのは、やたら退屈で、面白かったのはここで出会った仲間や彼らとの絆ぐらい。だったら、好きなことをやっちまおうとなったんだろう。
そして、仲間と相談を始めていた。捕らぬ狸のなんとやら... なんだろう。「じゃぁ、さ、これぐらいの金がかかるとしてさ、これぐらいチケットが売れたら、なんとかなるじゃん」ってな安易な発想で「儲かる」と話していた。その時は、ひとつ年下の音楽好きの後輩に同学年で、ジャズ・ピアノをやっていた女の子と合計3人。といっても、ちょいと惚れていた彼女はとっとと興味をなくして、後輩の二人で立ち上げたのがWalkin' Stepと名付けた呼び屋だ。なんで、この名前? さぁて、なんだろうね。当時好きだったブルース的なイメージを感じていたからってあたりじゃないかと思う。
ステージに立ってアコギを手に歌ったことはあるけど、PAのことなんてなんも知らんド素人のプロモーターの誕生だ。一番最初にやったのは、春一番時代の仲間で、当時、オレンジ・レコードというレーベルを作ってフォーク喫茶、ディラン周辺のミュージシャンのマネージメントなどを始めていた、同い年の仲間、通称、源さんとのコンタクト。そして、ディランⅡ(セカンド)を解散して、ソロ活動を始めていた大塚まさじのライヴをやることになる。バイトをしていた照明屋の師匠がほぼノーギャラで助けてくれて、PAに関しては「俺にやらせろ」と主張した、ジャズ喫茶、イリミテのマスターが担当。実を言えばこれが失敗で、照明をフルにしないとPAからノイズが出てくる... というので、ミュージシャンにはめちゃくちゃ迷惑をかけたものだ。
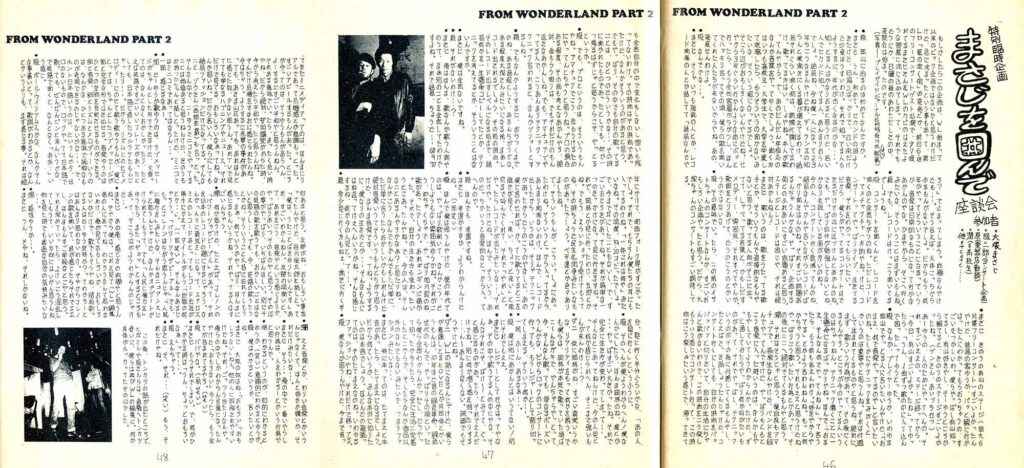
ド素人がなにかを始めると、無知がたたる... というか、アイデアの先走りで、とんでもないことをやらかすものだ。と、振り返って思う。最初の大塚まさじのライヴのチケットは、なんとマッチだった。って、意味、わかるかしら? 昔、喫茶店とかに行くともらえた、煙草に火をつける、あれです。今でこそチケットなんて色気もなにもないバーコードと情報しかないような代物で、それすらも消え去ろうとしているらしいけど、その昔、チケットもきちんとデザインされた「もの」だった。でも、ただの紙切れなんて、面白くない。というので、マッチ箱に写真と日付や場所が印刷されたものを作ったんだけど、当時コンサート・チケットを売っていたプレイガイドからは「危なくてこんなもの、おけるわけないでしょ!」とクレームの嵐。結局、プリントしたチケットを会場に持ってきたら、没になったマッチのチケットを受け取れるというようにしたなんてことがあった。
さらにプロモーションで放送局を訪ねるんだが、岡山にふたつしかなかったテレビ局のひとつでは、お偉いさんに「名刺も持っていないのか」と叱責されたこともある。それでも、もうひとつの局では担当者が真摯に話を聞いてくれたり... といっても、彼らがマイナーなミュージシャンのライヴにとりわけ関心を持ってくれるわけもない。結局は、愛車のホンダN360に飛び乗って、高校や大学まわりにポスターを貼りまくり、今ではフライヤーと呼ばれるようになったチラシを撒きまくるのがほぼ唯一の宣伝だった。

そんな頃に出会ったのが、岡山で「わんだあらんど」と呼ばれるミニコミを作っていた若者たち。SNSなんて夢どころか想像もできなかった70年代、メディアの中核を担っていた新聞や雑誌がマスメディアだとしたら、それに対抗するように頭角を現してきたのがミニコミと呼ばれる、自主出版で生まれた雑誌の数々。すでにこの頃、大阪ではオルタナティヴなイヴェント情報誌として「プレイガイド・ジャーナル」(通称「ぷがじゃ」)が、東京ではマス指向の「ぴあ」がある程度の支持者、読者を獲得してメジャーに匹敵する影響力を及ぼしていたが、岡山で同じような可能性を秘めていたのがこの雑誌だった。
なんとこれを作っていたのは10代半ばという高校生世代。中核を担っていた人物は高校をそうそうにドロップアウトした後、大学入学資格検定試験に受かってこのメディアを始めていたというから驚かされる。今、手元に1977年に出たVol.4があるんだが、その特集は「Good Tripしようよ」。目次を見ると、WL(わんだあらんど)24イン黒島、ピース・キャラバン77、マリファナ、性と心の解放といった言葉が目に入る。それだけでも彼らが時代の先端を遙かに超えて、どれほどぶっ飛んでいたかが手に取るようにわかる。しかも、WL24イン黒島とは、瀬戸内海に面する街、牛窓の港からすぐの小さな島で開催されたフェスティヴァル。ずっと後に、現在では山間部のキャンプ地に場所を移したナチュラル・キャンプと呼ばれるフェスを主催している仲間が、一時期、数年にわたって会場としていたのが、ほぼ無人島となったこの島だった。あれから20年を経てフジロックが生まれ、フェスティヴァル文化がこの国に根を下ろすことになる。そんなこと誰も想像できなかった時代にもこんなことが起きていたのだ。
彼らのみならず、その周辺からも音楽好きの高校生たちが集まってきて、チラシを巻いたり、チケットの手売りをして助けてくれるようになっていた。岡山に戻ってきて、当時の彼ら、特に中心になって動いてくれていた川根君と再会できればなぁと思っていたんだが、残念なことに、すでに他界したと知らされる。こういった人たちなくして、コンサート企画やそれを実現することはできなかった。今でも、どれほど言葉を並べても十分ではないと思えるほど彼らには感謝している。

端っから経営だとか、利益なんてことに執着していなかったからか、コンサートを開催しても、赤字となることが多かった。それを自分のバイトで稼いだ金で補填するという状態が続いていたんだが、チケットが完売して会場がパンパンになったこともある。記録を見ると、1977年7月27日に『生聞150分』と題して開催した憂歌団&シバのライヴ。「嫌んなったぁ」と始まるセルフ・タイトルのアルバムからカットされたシングル、「おそうじオバチャン」がヒットして... とはいっても、職業差別だとかなんとかいちゃもんを付けられて、放送自粛という名の「放送禁止」の憂き目に遭ったらしい。そして、77年に彼らのライヴの魅力を凝縮した『生聞59分』からは「パチンコ-ランラン・ブルース」もヒット。言うまでもなく、そのアルバム・タイトルをいただいたコンサートだった。
そこに、オープニング・アクト、いわゆる前座として大好きだったフォーク&ブルース・アーティストで画家でもあるシバ(三橋誠)に出演を依頼していた。彼も同じ年に名盤と呼ばれる『夜のこちら』というアルバムを発表。今でもときおり聞きたくなってこのレコードに針を落とすんだが、特に気に入っているのが「星の明日」という名曲だ。彼が漫画雑誌「ガロ」で発表していた絵のイメージが重なって、ウイスキーのTVCFにでも使ってくれたらヒットするに違いないなんて妄想したりもしていたものだ。
そのシバのライヴはこれを含めて3回やったかなぁ。最初は、当時表町商店街にあった長谷川楽器のホールでの単独公演。その前日に彼は奥さんと子供を連れて岡山にやってきて、学生時代の行きつけだった運動公園そばの小さな居酒屋「木の葉」で仲間と一緒にしこたま飲んだ記憶がある。帰り際、気付くとお銚子が何本もテーブルに並んでいたことからも想像できるように、翌日「二日酔いです」なんて言葉と一緒にライヴが始まっていた。
シバ(三橋誠)の名曲「星の明日」。1977年に発表されたアルバム『夜のこちら』(OFL-44)のB面一曲目に収録されている。このリンクはライヴ音源を使っているようで、スクリーンには彼のアーティスト、漫画家、画家としての作品の一部が使われているのではなかろうか。
実は、そのときのライヴをジャズ喫茶、イリミテのマスターが録音してくれて、そのオープン・リールのテープがまだ手元にある。すでにプレイヤーを処分しているので、再生することはできないんだが、一度、ラジオの仕事をしている仲間に頼んでDATに起こしてもらったことがある。それを聞くと、ライヴを始める前に、まるで「決意表明」のような感じでオーディエンスに語りかける自分の声が聞こえる。「マイナーでも、売れていなくても、良質と思う音楽を岡山に紹介していきたい」とかなんとか。言うまでもなく、声は若々しく、話の内容は実にナイーヴで青臭い。ここ10数年、フジロックの前夜祭でオーディエンスに声をかけるようなことをしてきたんだが、似たようなものだろう。ひょっとすると、自分はあの頃からなんも成長していないのかもしれない。
すでに記憶があいまいで、どんなアーティストのライヴをやったのか、はっきりとは思い出せない。ウィーピング・ハープ妹尾バンドはやったし、西岡恭蔵もやっている。長谷川楽器の前で彼と握手したとき、まるで自分の手を握りしめるような力強さに驚かされたのが鮮明な記憶となって残っている。彼がそれから30年ほどの後に自殺したとき、彼のデビュー・アルバム『ディランにて』を聴きながら涙を流すことになるとは。ここに収められた曲「君の窓から」で「死にたいなんて言わないで」と歌っていたじゃないかと、心の中でつぶやくんだが、このフレーズがどんどん悲しみを増幅していったのを忘れることができないでいる。
そんな未来があるなんぞ微塵も想像できなかったあの頃、闇雲に突っ走っていた自分に救いがやってくることになる。それがなにかは次回に続きます。
レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬更新を目指しておりますが、毎度遅れ気味で申し訳ありません。次回更新も2月中旬がめどとなります。お楽しみに!
【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら
[prof01] [prof01_main]
[prof01_main]
花房浩一
(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)
1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。
月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。
FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。
一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。
96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]
©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。









