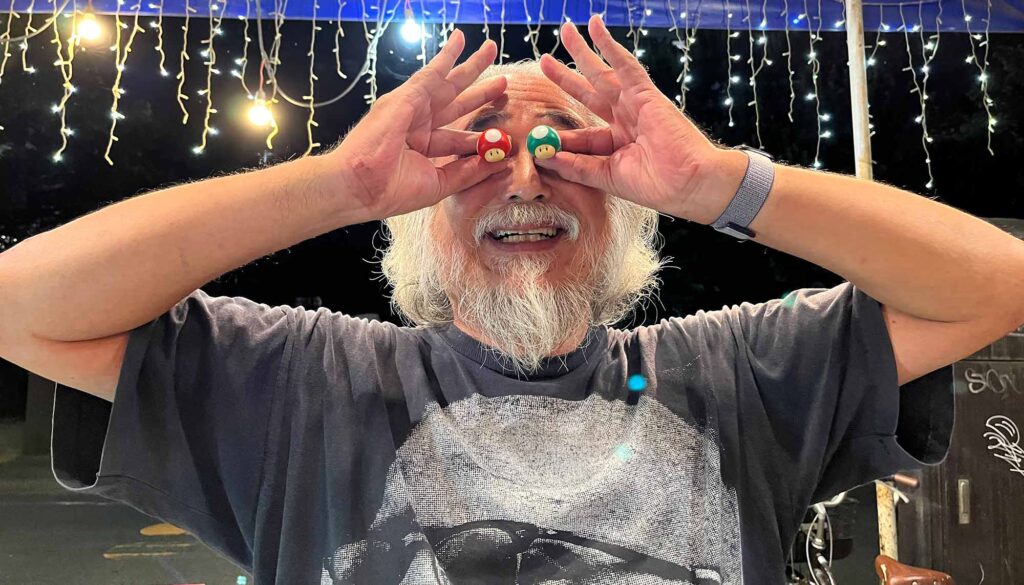10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第30話は初の断捨離体験も済ませて、初体験となる海外への旅の準備におおわらわのてんてこまい。
真っ赤っかに輝く夕陽があまりに眩しすぎて、「や〜めたぁ」と、レコード屋稼業から足を洗っていた。と、書き始めると、ちょいとかっこいいんだが、全く意味不明だな。でも、タバコ休憩の時に、大手スーパーの裏部屋のような休憩室の窓越しに見たそんな光景をきっかけに、日々の変化を楽しむこともできない生活の連続への疑問を感じて、それが「辞める」引き金になったのは間違いない。まずは「本当にやりたいこと」をやるべきで、「金を貯めなきゃ」って言い訳をしながら、時間を浪費しているのではないか... と、思えるようになっていた。

卒業に必要な単位だけ取って、卒業式なんぞほったらかして、名古屋のレコード屋で働き始めてたのは1979年3月だった。それからずっと居候をしていた店長の家を引き払って実家に戻ったのはその翌年。新しい年が明けてしばらくの後だった。ずっと暖めていた日本脱出作戦を決行する二ヶ月ほど前だったと思う。
おそらく、日本を飛び出すために着々と進めていた準備作業が、その頃に一段落していたってことなんだろう。といっても、なにをどう進めていたのか... なかなか思い出せない。今のようにネットをググれば、すぐに情報を得られるようになるなんて想像もできなかった時代。コンピュータなんぞ、テレビや映画のSFで見るだけの夢物語だった。情報源は書籍がメインで、「留学ジャーナル」なんて雑誌もチェックしながら、いろいろなところから情報を拾い集めていたようだ。
まずは語学留学をして、ある程度英語を話せるようになったら、ヒッチハイクの旅でもしてみよう... というのが当初のプラン。そこで選んだのは日本人がいないだろうと思えた田舎の学校だった。まずは、否応なしに英語を話さないといけない立場に自分を追い込みたいというので、なにはともあれロンドンは避けていた。個人旅行は一般的ではなかったとは言え、団体旅行で人気だったのが、昔のたたずまいを残していたイギリスの首都。日本企業の海外進出も加速して、会社員もいっぱいいたようだし、ロンドンの語学学校が日本人に人気だという噂は耳にしていた。せっかく出かけていっても、まわりが日本人ばかりだったら、結局イージーな方向に流れて、勉強にはならんだろと、そう思ったのが理由だ。
結果として、選択したのはイングランド西部のデヴォン州にあるトーキーという小さな町にある学校なんだが、それがどんな町なのか全く知らなかった。それどころか、イギリスという国に関する知識も皆無に近かった。あれほど音楽に親しんでいながら、この時点で、UKのロックやポップスにほとんど関心がなかったといっていい。「あんた珍しいね」とよく言われるんだが、実のところ、この時点でビートルズやストーンズのレコードは一枚も持ってはいなかった。一方で、はまっていたのはアメリカ西海岸からAORやジャズ・フュージョン系の音楽。といっても、その背景を掘り下げて、その魅力がどこから来るのか探ってみようなんてところまでにはいたっていなかったし、海外の音楽は趣味程度のものでしかなかったんだろう。それほどアメリカの音楽が好きならアメリカの学校に行けばいいものを... と思うはずなんだが、同じような経験をしていた知人が「英語を勉強するなら、イギリスだね。アメリカ人の上流階級の子供達も勉強するぐらいだから」というアドバイスを受けてこうなっていた。
語学学校に手紙を書いて、資料を取り寄せる。さらには、入学申請をして、授業料を送金する。当然のように、それを全部英語でやったことになる。代理店に頼むってな発想は持ち合わせてはいなかったし、そんなところがあったのも知らなかった。というので、全てをひとりでやっていた。それなら、英語の勉強なんてする必要ないじゃないかとも思えなくもない。もちろん、辞書を片手にやっているし、スムーズには行かなかったとはいえ、英語を書くことも読むこともできる。とはいえ、問題はからっきし話せない、聞こえてくる英語もわからないということ。だからこそ、英語が当然の土地で生活していくことで生きた言葉を勉強したかった。
そう言えば、手紙を書くのに役立ったのがタイプライターだった。っても、今じゃ、これも死語どころか、死滅しているのではないかと思うし、若い世代に関して言えば、それがなにかを知っている人でさえいないだろう。80年代には同じようにすでに化石のような存在となっているワープロが登場して、それがコンピューターに置き換わってからというものタイプライターなんぞ、「存在する価値」さえもないように思える。が、70年代以前の学生は、けっこう使っていたんじゃないかなぁ。愛用していたのはオリベッティの赤いヤツ... ってか、それ以外のメーカーは思い出せないほど、人気だったように思う。ガッチャンガッチャンとキーを打って、なんども手紙を書いて覚えたのがキー配列。そのおかげで、キーボードが絶対のコンピューターの世界になんのストレスを感じることもなく入っていけたのかもしれない。
探せばなんでもでてくるYouTube。自分が使っていたのはこれより後にでてきた安いモデルですが、基本的には変わらない。この独特の音が魅力なんだそうな。何度もミスタイプして修正液で直す... なんて体験をした人が同世代にはいっぱいいたのではないかしら。
語学留学に始まる海外脱出への準備がかなりまとまって、実家に帰ってやったことと言えば、売れるものを売り払って金を作ることだった。といっても、今のように個人が単純にいろいろなものを売り買いできるような環境はなかったし、金目のものなんぞ持っているわけはない。というので、処分できるものと言えば、レコードのみ。あの頃、断捨離なんて言葉を耳にしたことはなかったんだが、おそらく、これが初めてのそれだったんだろう。
この時点で集めていたのは300枚ほどのLPだったと思う。なぜかLP指向でシングルを買った記憶はない。というので、そのうち100枚ぐらいを残して、学生時代からの仲間のようなお店、倉敷のグリーンハウスにコンタクト。個人的なつながりもあるし、餞別的な意味合いもあったのかどうか、けっこうな値段で買い取ってくれたように思う。
あの時残した約100枚は今も自宅にある。初めて買ったLP、はっぴいえんどのデビュー・アルバム、通称『ゆでめん』から『風街ろまん』に加川良や友部正人といった日本のフォークロックから、ミシシッピー・ジョン・ハートやブラウニー・マギーとソニー・テリーといったカントリー・ブルース、ビッグ・ママ・ソーントンやオーティス・スパンあたりのシカゴ・ブルース、デヴィッド・グリスマンのジャズっぽいカントリー系、ECMレーベルを代表するキース・ジャケットやラルフ・タウナーの作品やフリー・ジャズのアルバート・アイラーから、ジャクソン・ブラウンにトム・ウェイツといったシンガー&ソングライターの作品の数々。何度も何度も針を落として聞き惚れていたレコードを残して、けっこうな数を売ったというのに、何を売ったのかほとんど覚えてはいない。
このあたり、冷静に考えると、音楽好きの奇妙な性を読み取れる。「もう何度も聞いた」んだったら、処分してもよさそうなものを、「だから残しておく」って発想ってなになんだろう。なんでこんな習性があるのかわからないが、どこかで音楽が消耗品ではないってことを教えてくれているのかもしれない。それぞれの音楽には付随した想いのようなものがあるように感じるし、それを触発してくれるのがジャケット・アート。おかげで、あれから40数年を経て、そんな昔のレコードに針を落とすと、当時とは違った音楽の響きを楽しむことができるようになった。不思議なものです。加えて、断捨離の意味も教えてくれていたような気がしないでもない。本当に愛している音盤なんぞ、100枚もあれば、充分かもしれない。なにせ、おそらく、ほとんどのレコードは聴かれることもなく棚にふんぞり返っているだけなんだから。

あの時売り払ったもので、唯一覚えているのは、ホーボーズ・コンサートの7枚組ボックス・セット。実を言えば、これは全く売れなかったようで、「あんた、これ探しとるんじゃろ、あげるわ」といってグリーンハウスのオーナーからいただいて、手元に戻ってきたことがある。これは1974年はじめから池袋のシアターグリーンで毎月1週間、当時、頭角を現してきた国内のフォーク&ロック系のアーティストやバンドを集めて開かれていたライヴの記録。フォーク系が中心なんだが、少しロックっぽい流れのなかにいた布谷文夫から小坂忠、センチメンタル・シティ・ロマンスあたりのライヴ音源が楽しめるのが嬉しかった。
それとどこかで重なっていたのが、そのしばらく前、まだ高校生の頃にほぼ毎回チケットを買っていた六番町コンサートだった。大阪は難波にある高島屋の7階だっけかのホールで毎月開催されていて、そのプロデューサーは春一番を立ち上げた福岡風太。わずか100円のチケットで、同じような流れにいるアーテイストのライヴを毎月楽しむことができた。もうずいぶん昔のことなので、記憶はあやふやなんだが、確か、山下洋輔トリオと友部正人が同じステージでやらなかったかなぁ... なんて思ってもみるが、全然、確証はない。
そんなイヴェント情報を得るのに絶対的な存在だったのが、大阪を中心に関西の、いわゆる、オルタナティヴな情報誌、プレイガイド・ジャーナル(通称、プガジャ)。音楽や演劇のみならず、旅の情報もあったように記憶していて、そこでよく宣伝していたマイナーな旅行代理店、アイランドで人生初のフライト・チケットを買うことになる。うろ覚えだが、ひょっとして、この事務所、プガジャと同じ場所になかったかなぁ。いずれにせよ、いわゆるカウンター・カルチャー的なことをやっている人達は、どこかで繋がっていたように思う。面白いのは、このチケットを買ったときに顔を合わせた代理店の方と、それから数十年後に、東京は中目黒にあるエチオピア・レストランで鉢合わせしたことかもしれない。人生ってのは、摩訶不思議なつながりを生み出してくれる。
あの頃の航空機技術も今と比較したら、まだまだ発展途上だったんだろう。当時は、日本からヨーロッパへの直行便は存在しなかった。途中で給油の必要もあって、たいていはアラスカのアンカレッジ経由で、自分のフライトもそれだった。大阪の伊丹空港から韓国の金浦空港を経由。実に長いトランジットを経てアンカレッジに飛んで、さらにパリで再びエール・フランスのフライトに乗り換える。それでイギリスに入るのだが、空の玄関として有名なヒースローではなく、ガトウィックというロンドンの南、ブライトンという町への途中にある空港に降り立っていた。初めてのフライトなので、目的地にたどり着けば、それで充分。ヒースローがメインの空港だとか、そんなことさえ知らなかったが、気にもかけていなかった。
今じゃ、直行便で12時間ほどで東京からロンドンへたどり着く。最短だったのは評判が悪かった旧ソヴィエト連邦時代のエアロ・フロートでモスクワ経由のルートは15時間。アラスカ経由は18時間だった。ある時期、給油ポイントとして重要な役割を果たしていたアンカレッジ空港に溢れかえるようになったのが、バブル時代に向かってどんどん海外旅行熱が広がった日本人旅行客。彼らのために日本語を話すスタッフがいっぱいいたし、日本料理の店もふんだんにあったんだが、今はどうしているんだろう。おそらく、アメリカでもきわめてマイナーな空港になっているのではないかと察する。
同様に時代の変化を感じさせるもうひとつが、金にまつわる話かもしれない。70年代から80年代と、日本人の大多数に全く縁がなかったのがクレジット・カード。最近じゃぁ学生だって1枚や2枚は持っているそれがなになのかを知る人もほとんどいなかった。いうまでもなく、キャッシュレスなんて論外で、旅をするのにまとまった金を持ち出すのが普通だった。とはいっても、現金の持ち出しには制限があって、自分のように1年間を海外で過ごそうとしている人間は、なんらかの方法を探し出さなければいけなかった。
じゃぁ、どうする? そんな情報を教えてくれたのが、あの当時から、じわじわと人気を獲得し始めた、バックパッカー必読の書となった『地球の歩き方』という本ではなかったかと思う。おそらく、ここで旅行小切手(Traveller's Checkが省略されてT/Cと呼ばれることもあった)の存在を知ったのではないか。これは基本的にはそれぞれの個人の名前を記す金券のようなもので、一般的に人気だったのは米ドルもの。世界で最も安定した基軸通貨だというのが理由なんだろう。それを各国の銀行で現地通貨に両替することができるというので、適当な額面の米ドル旅行小切手を何10枚か用意することになる。もちろん、どの国に行っても、現金を両替することができるんだが、盗難に遭遇したら、それで終わり。盗まれた金なんぞ戻ってくるわけはない。が、これは、そうなったときにも再発行してくれるというので、当時の旅行客にはかなり重宝されたはずだ。
そんなアイデアを生み出したのが、19世紀から旅行代理店として発展したイギリスのトーマス・クックという会社で、世界で初めて、パッケージ・ツアーを企画したといわれている。この会社に関して言えば、旅行小切手同様に有名だったのが、全ヨーロッパを網羅した列車の時刻表。おそらく、洋書を売っている書店でその時刻表を買ってきて、ガトウィック空港に到着してから、デヴォン州のトーキーまでどう行けばいいかを入念にチェックしたんだろう。ガトウィックからロンドンのヴィクトリア駅に出て、それからTube(あるいは、アンダーグランドが正しい英語。サブウエイは米語)と呼ばれる地下鉄で、イングランド西部への鉄道のターミナルであるパディントンへ移動。そこから長距離列車でデヴォンのトーキー駅にたどり着くんだが、あらかじめ手紙でこの予定を知らせていたからか、地元でお世話になる下宿の夫婦がオンタイムでこの駅まで迎えに来てくれていたなんてこともあった。
今ではアプリかなにかを使って列車に乗れるんだろうか? インターレイル・パスは健在のようで、この映像だけでも旅の魅力を感じさせてくれる。ヨーロッパを鉄道で旅するにはこれがベストじゃないかなぁ。
その時刻表か、あるいは、『地球の歩き方』で知ったんだろう、初の海外だからヨーロッパも旅してみようと、一定期間、ヨーロッパ中の鉄道に乗り放題という周遊券インターレイルパスも買っていた。それを真似て生まれたんだろう、JR(日本鉄道)パスは海外から日本に来る旅行者用で、それを使って日本を旅行している若者を見ると、当時の自分を思い出す。「のぞみ」や「みずほ」といった最速新幹線では使えないが、その他は大丈夫というので、彼らが使うのは「ひかり」がメイン。実は、30%の運賃割引が適用されるというので、1年半ほど前から高齢者向けの『ジパング倶楽部』に入会しているのだが、これでも同じように「のぞみ」には乗れない。というので、少し時間はかかるんだが、「ひかり」で大阪や東京に向かうとやたら外国人旅行者に出会うのは、彼らがこのJRパスを使っているからだろう。
最初に3ヶ月ほどホームステイをして、イングランドを中心にヒッチハイクの旅をする。それからまたしばらく語学学校の短期コースを受けて、ヨーロッパに出る... と、そのあたりまではある程度の計画を練っていたんだが、その後のことはな〜んも考えてはいなかった。基本的には丸1年をかけて、いろんなところを旅してみようと、けっこうがっしりしたフレーム付きのバックパックを購入して、準備万端整ったのが1980年の3月末あたりだった。
日本を離れたのは4月12日ではなかったかと思う。大阪の伊丹空港から旅に出るんだが、その前日、大阪新南部にある実家への最寄りの駅、萩原天神から難波に出かけたとき、なにやら象徴的な出来事に出くわすことになる。上りのホームで電車を待っていると、目に入ったのが向かいのホームで日傘を差してロリータ系の服を着たおばさん(と見えた)。「変な雰囲気だなぁ」と思いつつ、なにげに彼女を見ていたんだが、下りの急行が走り込んでくると、同時に、彼女も視界から消えていた。飛び込み自殺だった。列車はホームを過ぎたあたりで急停車し、その後の線路の真ん中に横たわっていたのが彼女。ぴくりとも動かなかったから、即死だったんだろう。といっても、その姿を凝視したわけではないんだが、そう感じていた。
その直後から自分を包み込む空気が凍り付いたように感じていた。同じホームにいた女性と目が合うと、いかにもおぞましいといった表情を見せている。ところが、上りの電車が入ってきて乗り込むと、目の前に広がっていたのは何事もない当たり前の日常。誰ひとりとして、この事件に気付いてはいない。この時、なにやら自分が全く違う世界に引きずり込まれたように感じていた。それは車内だけではなく、終着の難波で電車を降りてからも同じこと。なにやら普通の世界から遊離された空気の中を漂っているような感覚に陥っていた。これが、日本を飛び出す前日の出来事。ひょっとしたら、1年におよぶ旅で体験する波瀾万丈の経験を暗示させていたのかもしれない。
と、話は初のフライトから、海外脱出でなにを見たかってことに転がっていく... はずね。
レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬更新を目指しております。が、残念ながら、月末にずれ込んでしましました。陳謝。次回こそは10月中旬に。お楽しみに!
【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら
[prof01] [prof01_main]
[prof01_main]
花房浩一
(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)
1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。
月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。
FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。
一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。
96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]
©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。